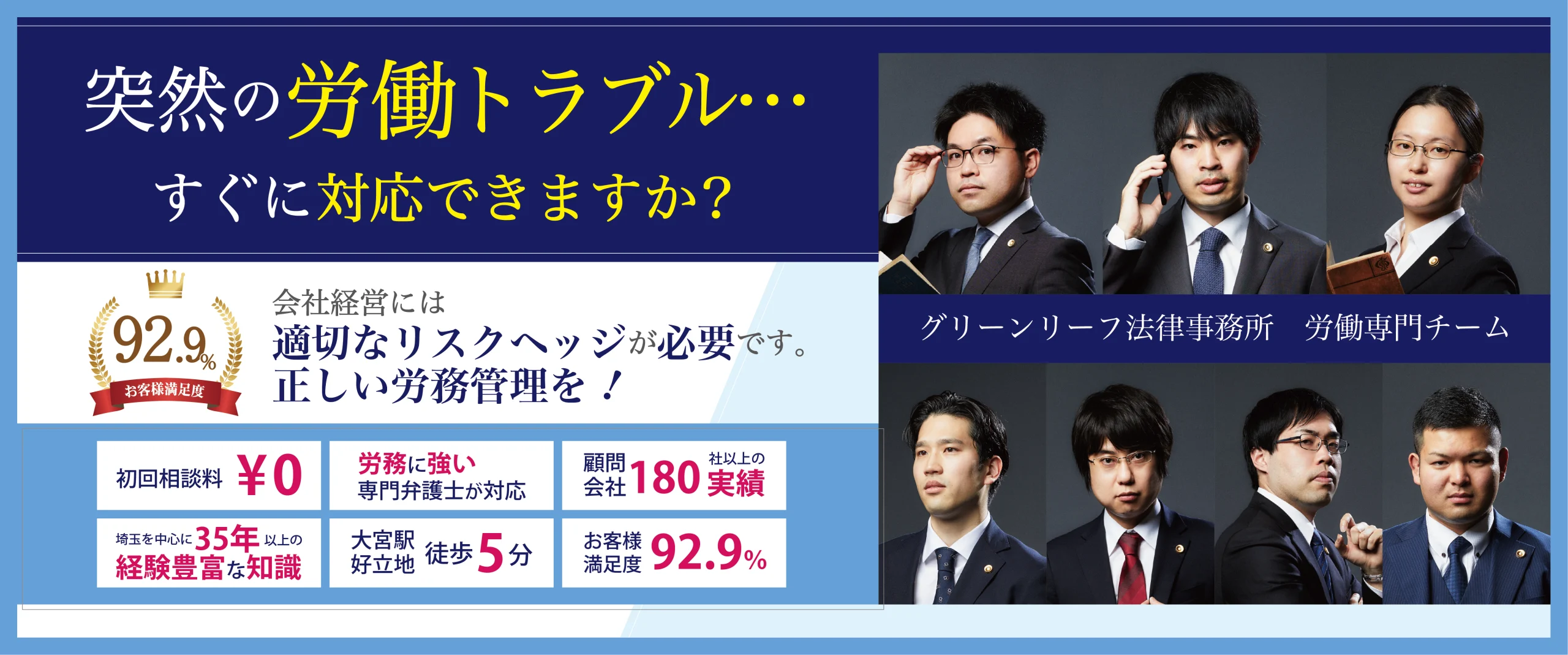企業間取引において、代金の未払いは大きな経営課題であり、未払いは会社の存続に関わる重大な問題です。しかし、感情的に対応すると事態が悪化する可能性もあります。冷静かつ法的な手続きに則って対処することが、早期解決への鍵となります。
本コラムでは、取引先との代金未払いトラブルに直面した際に、企業の方が取るべき具体的な対処法を、ご案内いたします。
状況の確認と証拠の収集

まずは、冷静に状況を整理して必要な情報を集めることが必要です。
これは、後の法的手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
債権の存在と金額の確認
契約書・発注書・請求書
取引の根拠となる書類をすべて確認します。契約内容、納品物の詳細、金額、支払い期日を明確にしておきましょう。
納品書・受領書
商品やサービスが確かに相手に提供されたことを証明する書類です。これらがなければ、相手から「納品されていない」と主張される可能性があります。
メールやFAXの履歴
支払いに関するやり取りの記録は、相手が未払いを認識していることの証拠になります。
担当者との会話メモ
口頭でのやり取りも、日時、相手の名前、会話内容などを記録しておきましょう。
これらの証拠は、最終的に裁判になった際にも重要な役割を果たします。できるだけ網羅的に集めておくことが大切です。
相手企業の状況把握
会社の所在地、代表者名
法的な書類を送付する際に必要となります。登記簿謄本を取得して、最新の情報を確認することも有効です。
経営状況
倒産寸前であったり、すでに夜逃げしていたりする場合、手間と費用をかけても債権回収が困難になる可能性があります。信用調査会社を利用したり、インターネットで情報を検索したりして、相手の状況を把握しましょう。
任意での交渉

証拠が整ったら、まずは相手と直接交渉し、自主的な支払いを促します。この段階で解決すれば、費用も時間も最小限で済むため、まずはこのような試みをすべきです。
電話やメールでの催促
最初の連絡は、穏やかな口調で、支払い期日を過ぎていることを伝えることから始めましょう。相手が単に支払いを忘れているだけの可能性もあります。
①冷静に、客観的な事実のみを伝える
(例)「〇月〇日付の請求書、金額〇〇円が未払いとなっております。お振込み状況をご確認いただけますでしょうか?」
②期限を明確にする
(例)「〇月〇日までに、お振込みをお願いいたします。」
③今後の法的手続きを示唆する
(例)「期日までにご入金がない場合、法的措置を検討せざるを得なくなります。」という一文を添えることで、相手にプレッシャーを与えることができます。
なお、連絡する際には、以下の点に注意をすると今後スムーズなやり取りが期待できます。
督促状・内容証明郵便の送付
口頭での催促で効果がない場合、書面で意思表示をすることが重要です。
普通郵便の督促状
普通郵便で督促状を送付が考えられます。督促状を送ることで、相手に事の重大性を認識させることがで切るかもしれません。
なお、疑義が生じないように、督促状には、未払い債権の詳細(請求書の番号、金額、支払い期日)、支払い期限、振込先を明記するべきです。
内容証明郵便
内容証明郵便は、「いつ、誰から、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
内容証明郵便を送付するメリットとしては、相手に「本気で回収するつもりだ」という強い意思を伝えられるという点、裁判になった際、相手が「そんな手紙は受け取っていない」と主張することを防げる点などがあります。
内容証明郵便のもっとも大きなメリットは、時効の完成を猶予できる点にあります。
債権には時効がありますが、内容証明郵便を送付することで時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。
なお、内容証明郵便を発送する際には、1枚の文字数、行数に制限があるため、規定に則って作成する必要があるため、こうした点には注意が必要です。
内容証明郵便の書き方に不安がある場合は、弁護士に依頼するのが確実です。
法的手続きの検討と実行

任意での交渉が不調に終わった場合、裁判所を介した法的手続きを検討します。主な選択肢は以下の通りです。
支払督促
支払督促とは、相手に未払い代金を支払うよう裁判所から督促してもらう手続きです。相手が異議を申し立てなければ、訴訟を経ずに強制執行が可能となります。
1 申立て:裁判所に支払督促の申立てを行います。
2 審査・督促:書類審査が行われ、問題がなければ裁判所から相手に支払督促が送達されます。
3 異議申立て:相手が送達から2週間以内に異議を申し立てなかった場合、債権者は仮執行宣言の申立てができます。
4 仮執行宣言:仮執行宣言が付された支払督促は、確定判決と同じ効力を持ち、強制執行が可能になります。
支払督促の流れは、以下のとおりです。
支払い督促のメリットとしては、訴訟に比べて手続きが簡易で、費用も安く済むという点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、相手が異議を申し立てた場合、通常訴訟に移行するため、手続きが二度手間になる可能性がある点が挙げられます。
少額訴訟
60万円以下の金銭債権に限って利用できる、簡易で迅速な裁判手続きです。
原則として1回の期日で審理を終え、即日判決が下されます。
1 訴えの提起:簡易裁判所に訴状を提出します。
2 第1回期日:裁判官、原告(申立人)、被告(相手)が同席し、双方の主張や証拠を基に審理を行います。
3 判決:原則としてその日のうちに判決が言い渡されます。
少額訴訟の流れは、以下のとおりです。
少額訴訟のメリットとしては、迅速に解決できるため、時間や費用が抑えらる点にあります。
一方、デメリットは、60万円を超える債権には利用できない点です。また、相手が少額訴訟での審理に異議を唱えた場合、通常訴訟に移行しますので、その場合には結果的に迅速な解決にならない点も挙げられます。さらに同一の裁判所では年に10回までしか利用できないという制限があります。
通常訴訟
少額訴訟の対象とならない高額な債権や、事実関係が複雑なケースでは、通常訴訟を選択します。
1 訴えの提起:地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出します。
2 口頭弁論:数回にわたる口頭弁論(期日)が繰り返され、双方の主張や証拠が吟味されます。
3 和解または判決:審理の途中で和解に至ることもありますが、合意に至らない場合は裁判官が判決を下します。
通常訴訟の流れは、以下のとおりです。
訴訟のメリットとしては、金額の制限がなく、複雑な事案にも対応できるという点が挙げられます。一方、デメリットとしては解決までに長期間(半年〜数年)を要することが多く、弁護士費用も高額になりがちという点です。
とはいえ、相手方が任意で支払いに応じてこず、さらに少額訴訟などの手続きが奏功しない場合には、最終的には通常訴訟をするほかありません。
強制執行

支払督促や訴訟で勝訴し、相手がそれでも支払いに応じない場合、強制的に債権を回収するほかありません。その手続として強制執行が法律上用意されております。
これは、確定判決や仮執行宣言付きの支払督促などを根拠に、裁判所の執行官が相手の財産を差し押さえ、債権の回収を図る手続きです。
もっとも、強制執行は、相手の財産を特定する必要があるため、事前の調査が重要です。
相手の取引銀行や取引先が不明な場合は、弁護士会照会などを通じて調査することもあります。
なお、最終的に、相手方の銀行口座にお金がない、あるいはその他にも全く財産がないという場合には、強制執行をしても結局お金を回収できないというケースもあることには注意が必要です。
まとめ

代金未払いトラブルに弁護士は敷居が高いと感じる方もいるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することで、交渉の代行・法的手続きの代行などを任せることができますから、適切な債権回収が期待できます。
また、未払いトラブルは精神的にも大きな負担となります。弁護士に任せることで、本業に集中できるようになるというメリットもあります。
代金未払いは、放置すればするほど回収が困難になる傾向があります。まずは一度、弁護士にご相談いただけますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。