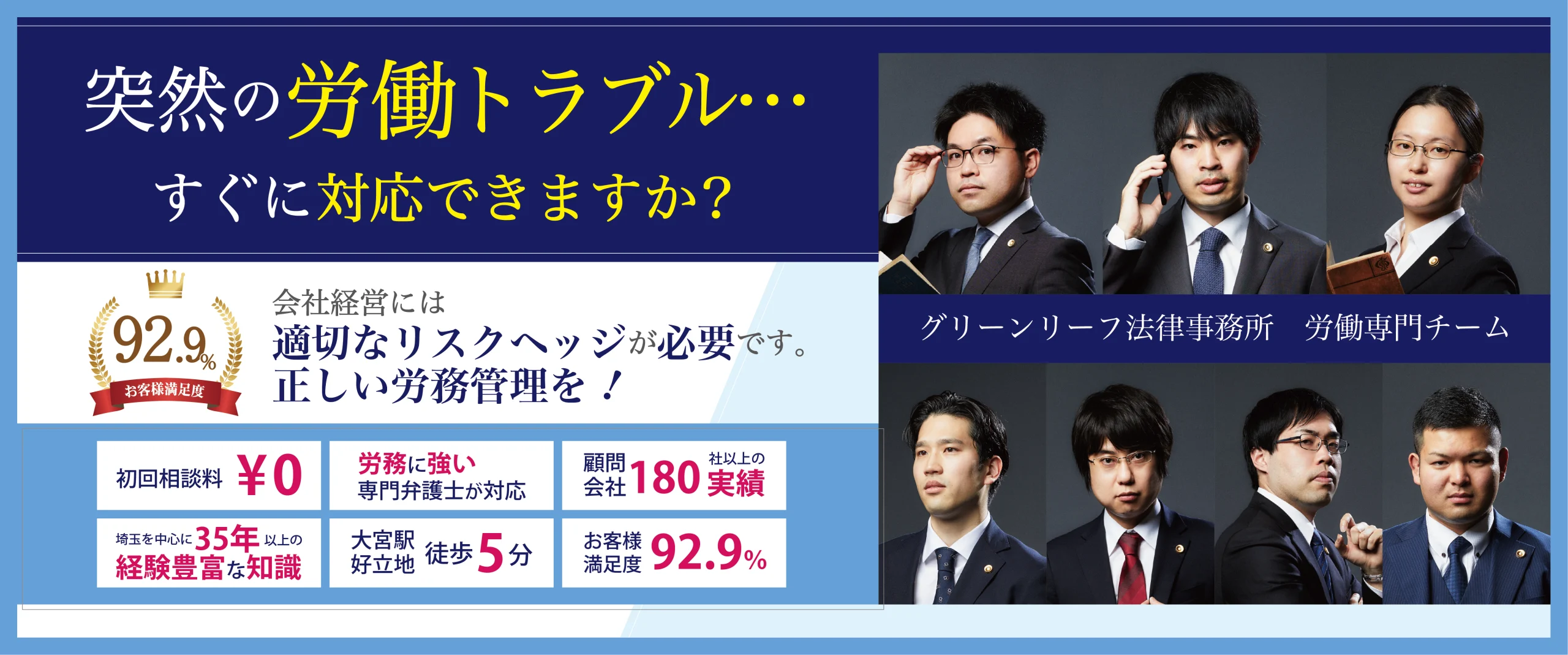コンプライアンス遵守の重要性は、ニュース等でもひろく世間に知れ渡っているものと思われますが、なおハラスメント問題は生じており、この問題に会社が厳格に対応すべきことは当然のことです。ただ、会社のハラスメントへの対応が不適法となってしまっては意味がありません。そこで、今回は以前の「ハラスメントが発生した際の会社の措置について 前編(不適切事案)」というコラムに引き続き、近時の裁判例において会社のハラスメントに対する対応が問題となったものを複数取り上げ、その傾向をご説明いたします。今回は後編として、適切とされた案件を解説します。
会社のハラスメントに対する対応について

法律上の措置義務について
セクシャルハラスメントについては男女雇用機会均等法にて、パワーハラスメントについても労働施策総合推進法にて、それぞれハラスメントに対する措置を会社に義務付けています。
これらの法律により会社は、従業員等のために相談窓口や就業規則などの整備、広報などによる周知・啓発をすることが必要とされています。
ただ、法律施行後もなおハラスメント事件は後を絶たず、厚労省が公表している「民事上の個別労働関係紛争」の相談内容としては、延べ316,072件の相談件数のうち、「いじめ・嫌がらせ」というパワハラが問題となる項目が全体の17.4%・54,987件を占めるとされており、件数としてはトップとされています。
このようなハラスメント事件が多い背景としては、会社としての措置が十分でないという要素も考えられるところであり、逆に適正な措置の重要性が浮き彫りになっているといえます。
裁判例に見られる会社の措置が「適切」とされた事例

東京地方裁判所平成17年1月31日判決
<事案の概要>
原告Xさんは、従業員約6000名を擁するコンピューター関連の会社Yの執行役員に次ぐ地位にあったところ、平成15年7月17日に、部下の女性従業員AさんやBさんらに対しセクハラ行為(日常的に性的な発言をしたり、身体的接触を繰り返した上、Aさんに対しては飲食を共にした際に無理やりキスをしたり、深夜自宅付近まで押し掛けて自動車に乗せ、車中で手を握るなどし、Bさんに対しては残業中に胸に触ったと認定されていました。)をしたとして、会社Yから懲戒解雇処分を受けました。
Xさんは、
・セクハラ行為の事実を否認
・懲戒解雇処分について手続的要件を履践していないので無効と主張
して、Yに対し、雇用契約に基づく従業員の地位にあることの確認及び賃金の支払を求めました。
本判決では、Xさんのセクハラ行為の嫌疑につき、
①Aさんの供述は、多岐にわたるもので、それぞれが具体的かつ詳細であり、不自然・不合理な点は見当たらないこと、
②Aさんの供述は、会社からの事情聴取時点から既に具体的かつ詳細なものであり、その後も当審の証言まで概ね一貫していること、
③AさんはXさんから高い評価を得ていたおり、Aさんが殊更虚偽の供述をしてまでXさんを陥れなければならないような事情はうかがえないこと、
④そもそもAさんが異動を希望していた理由は、Xさんのセクハラ行為から逃れるためであったのであるから、XさんがYの人事部から異動をほのめかされて虚偽のセクハラ行為を申告したとは考え難いこと、
⑤Aさんは27歳の独身女性であるところ、Xさんから身体を触られたりキスをされたと第三者に述べることは、相当な心理的抵抗があったものと推認することができ、実際、Aさんの方からYに対しXさんを積極的に訴えたというものではなく、Aさんは当初Yからの事情聴取においては当初供述することを拒んでさえいたこと
などを考慮して、Aさんの供述には信憑性があると判示し、否認するXさんの主張を容れず、認定をしました。またBさんの供述についても、各種の観点から検討を加え、信憑性があると判示し、認定しました。
さらにYがXさんを懲戒解雇するに当たって、弁明の機会を付与したかなど手続的要件を履践したか否かも問題となりましたが、本判決では、「一般論としては、適正手続保障の見地からみて、懲戒処分に際し、被懲戒者に対し弁明の機会を与えることが望ましいが、就業規則に弁明の機会付与の規定がない以上、弁明の機会を付与しなかったことをもって直ちに当該懲戒処分が無効になると解することは困難というべきである。」としながら、仮に、Xさんの主張を前提としても、本件では、Xさんには、本件懲戒解雇の際、Yから一応弁明の機会を付与されていたものと評価することができるとして、Xさんの主張を斥けました。
以上の結果、本判決は、本件懲戒解雇を有効と判断し、Xの請求を棄却しました。
<本件のポイント>

セクハラ行為が問題となる場合、セクハラをしていないという加害者と、セクハラを受けたと主張する被害者との供述が対立し、第三者的な客観的証拠が乏しいというケースが多いと思われ、そうすると加害者とされる者・被害者とされる者、どちらの言い分に理由があるかが問題となることもあります。そのような場合に、本件判決のような事実認定をし、問題行為の存否を判断するということが一つの視点となるでしょう。
また、本件では懲戒解雇するに当たって、従業員に対する弁明の機会を与える必要があるのか否かも問題になっています。「就業規則等に規定がない場合には、弁明の機会を与えることは懲戒解雇の有効要件とはならない」としている裁判例もありますが、結論としては本件でも弁明の機会を与えることが望ましいこと、実際にはXさんに弁明の機会が与えられていたことも認定しているため、やはり懲戒処分の有効性を争われないためには、そのような弁明の機会を与えること、さらにはその点を明確に就業規則等に記載しておくことが良いといえるでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。